
犬や猫、大切なペット達の現在の聴力はどのくらいなのか、あなたは把握されてるでしょうか。
当院では治りにくい外耳炎や中耳炎の完治、またはかなりの回復状態まで導く事ができた実績があります。
ここでは犬や猫の外耳炎に関する基礎的な知識から実際の症例、治療法、発症している際のしぐさなどをご紹介しています。
わんちゃんたちは耳を患っているだけで、かゆみや頭痛、憂鬱感で悩まされています。
当院は、それを少しでも早く回復させる事で、今以上に快活で良好な飼い主様とわんちゃん達のコミュニケーションを得るお手伝いが出来ればと願っています。
外耳炎は、耳の穴に急性または慢性の炎症が起こっている疾患のことをいいます。
その炎症は、耳の穴の入口から鼓膜まで及ぶこともあり、放っておくと鼓膜の奥にある中耳、さらには内耳に波及することも珍しくありません。
症状は、外耳炎を引き起こしている原因と炎症の程度により様々ですが、一般に耳にかゆみや痛みが生じます。痛みのため、犬自身が耳を触らせまいと、攻撃的になることすらあります。
そのほかにも、首を振ったり足で耳の後ろの部分を掻いたり、耳を下にして頭を傾けるようなしぐさをします。
耳垢が多くなり、耳から悪臭を放つようになって、ようやく気が付かれることもあります
原因として、最も多いのが犬アトピー性皮膚炎あるいは食物アレルギーです。
実に犬アトピー性皮膚炎のわんちゃんの83%は、外耳炎を併発しているという報告、そして犬アトピー性皮膚炎のわんちゃんの35%は外耳炎の症状のみというデータもあります。
一方、食物アレルギーのわんちゃんの80%は、外耳炎を併発しているとも言われています。
このように、外耳炎の多くがアレルギー体質に関連していることがありますが、他にも草の実など異物によるもの、耳疥癬(耳ダニ)の感染によるもの、綿棒などによる誤ったケアによるもの、内分泌と呼ばれる体質によるもの、免疫の問題によるもの、腫瘍によるもの、耳垢腺という分泌腺の疾患によるものなど多くの原因がありえます。
もともと、耳の中には『マイグレーション』と言って、耳の中を自浄化する自然治癒力があるのですが、上記のような外耳炎を引き起こす原因によって、そうした機能が働かなくなると、耳の中の環境が悪化し、外耳炎が発症します。その結果として、細菌や真菌が増えるわけです。
外耳炎は、こうして様々な原因がありますから、これまでの経緯を詳しくお聴きしていくことが必要です。
また、オトスコープという内視鏡で耳の中を丁寧に診てもらうことが望まれます。
オトスコープとは
獣医師用の耳用内視鏡(耳鏡)。パソコンやタブレットを使用して動物の耳の中を見ることができる。
コデン株式会社より引用
私は、「刺毛性鼓膜炎」と名付けた、体表にある被毛が鼓膜を刺激、もしくは刺さることによって起こる外耳炎をたくさん診ています。
これなどは、オトスコープでないと、見つけることが難しいでしょう。
どのケースも「細胞診」という耳垢の検査が必要です。なぜかというと、この検査によって外耳炎の原因や性状がわかることが多いからです。
こうした検査があってはじめて「的を射た治療」ができます。すなわち、外耳炎の治療法は外耳炎をもたらした原因によるのであり「抗生物質」の投与で治ることは、むしろ少ないと言えるでしょう。
外耳炎をもたらした原因に焦点を当てつつ、必要により細菌や真菌を退治します。慢性になってしまった外耳炎の多くは、バイオフィルムというしつこい汚れの中に細菌が生き残っています。ですから、丁寧に汚れを洗い落とさないと完治しにくいと思われます。
患者であるわんちゃんたちは、言葉では表現しませんが、外耳炎が慢性でしかも悪化しているとかなり辛いです。飼い主がわんちゃんの状態を見極め早期な治療や定期的な健診をお受けになることをお勧めします。

耳の中(外耳道)や耳のまわりの炎症をいいます。
実は、犬ではあらゆる病気の中で最も多い疾患の一つです。
原因は様々で、しかも複数の因子が関係していることが多く、そのため治りきらずに慢性になりやすいのです。
症状
外耳炎ではこのように耳垢がへばりついていることがあります。
こうして洗浄いたします。
治癒した時の状態です。
犬や猫では、ほとんどの場合、外耳道から波及して鼓膜の奥にある中耳まで炎症が起こり、中耳炎となります。例外的にキャバリアと一部の犬種では、鼻の奥から耳管と呼ばれる管を介して中耳炎になります。
中耳炎の症状は、ほとんど外耳炎と同じです。それだけに中耳炎になっていても気付いてもらえないことがよくあります。悪化した場合、頭を傾けたり、目が揺れる、顔面神経の麻痺などが見られます。
症状

破れた鼓膜が見えます。
破れた鼓膜から硬性鏡を挿入、鼓室も洗浄します。
中耳、外耳が清潔になると、こうして鼓膜は再生されやすくなります。
犬や猫では、外耳炎から中耳炎、そしてその奥にある内耳が侵されて内耳炎が発症します。ですから、内耳炎・中耳炎になってしまう前に外耳炎を完治させることが大切です。一方、ウサギでは、鼻から耳管という管を介して細菌が侵入し、内耳炎になることがあります。いずれも下記のような神経症状が出やすくなります。
尚、ここでは、ウサギの内耳炎の動画と治ってからの様子をご覧になれます。ウサギでは、ある種の原虫、エンセファリトゾーンによる感染症との鑑別が必要になります。
症状
頭を傾け、眼が揺れているウサギ。
外耳道と鼓室を洗浄、抗生剤を与えて治った様子。
よく見られるのが草の芒が、外耳道の奥まで入り込み、急性の外耳炎を発症します。
また、自分の毛が入って外耳炎が起こることもあります。
症状
外耳道に異物が入ると、炎症などの様々な病気を引き起こしてしまうことがあります。
症状は、犬がくびを振ったり、違和感のある側の耳を下に傾けるしぐさをを頻繁にします。
他に、外耳道が赤く腫れ上がる、鼓膜を破ってしまうなどが見られます。こうしたことで、中耳炎や内耳炎など、より深刻な病気を発症してしまうこともあります。
原因は、散歩などに行った際に草むらに入り、植物の種や虫が耳に入り込むことによって引き起こされることが知られています。しかしながら、実は体表の被毛が耳の穴に入り、鼓膜を刺激したり、刺さって起こるケースが最も多いと思われます。これまで、海外を含めこうした被毛による耳炎は知られていませんでしたので私は、「刺毛性鼓膜炎」と名付けています。
この「刺毛性鼓膜炎」は、全身麻酔をして、オトスコープという内視鏡を用いないと、見つけることすら困難と思われます。
犬のためにあなたができること
急に首を振ったり、頭を傾けるしぐさをすれば、すぐに動物クリニックへ
対策としては、できればオトスコープと呼ばれる内視鏡で診てもらうと良いでしょう。 異物は、それが何であれ、患者であるわんちゃんに全身麻酔をかけなければ、安全に、そして確実に取り除くことができません。また、異物は既に鼓膜や中耳、さらには内耳まで炎症をもたらしているかもしれません。このため、やはりオトスコープによる正確な診断と治療が勧められます。
かかりやすい犬の種類
全犬種が対象ですが、「刺毛性鼓膜炎」は特にパグ、フレンチブルドッグなど短頭種により多くみられる傾向があります。
草の芒を除去する様子。
自分の毛を除去する様子。
人間の場合と同様に、先天的難聴があります。犬では、その多くが遺伝性であると考えられています。
また、比較的まれですが、子犬の前庭機能障害による前庭性運動失調(運動に協調性が失われている)がみられ、難聴と関連している可能性があります。
既知の治療法はありませんが、ほとんどの場合、ペットとして受け入れられる存在です。
細菌性、ウィルス性、そして真菌性、さらには免疫性疾患も平衡感覚や聴力の喪失の原因となります。
MRIなどの画像診断は、中耳および内耳の関与を評価するだけでなく、脳幹への影響を除外するためにも必要です。
細菌性髄膜脳炎の発症を避けるために、全耳道切除術、あるいは腹側鼓室胞切開術が積極的に適応されますが、既述のようにオトスコープの活用法次第では、そうした手術を回避できるケースも増えています。
外傷などで、内耳がダメージを受けますと、一時的あるいは永続的な内耳の機能不全につながる可能性があります。
また、脳震盪の後ではたとえ骨折していなくても、内耳の問題が発症することはあります。
これは、犬の聴力喪失の最も一般的なタイプになります。
そうした場合、中耳インプラントは、一つの治療法になります。
代替的には、振動する首輪を使用して、飼い主さんとのコミュニケーションを改善することができます。
騒音による聴覚障害は、飛行、銃を用いた狩猟、住環境、MRIからの騒音などが、関連すると考えられます。
大きな騒音による聴覚の恒久的ダメージには、治療法がありません。そこで、犬の耳に保護具をつけてあげることが勧められています。
犬の中耳炎は、外耳炎と似ているため、見過ごされることが多いと思われます。
それは、私たち人間は、鼻や咽頭から細菌やウィルスなどが、耳管という中耳につながる管を介して、中耳へと感染して中耳炎を発症することが多く、激しい耳の痛みや閉塞感といった中耳炎独特の症状がみられるのに比べ、犬ではほとんどの場合、外耳炎が進行して中耳炎になるので、程度の差はありますが、症状としてはほとんど外耳炎と変わらないからです。
また、捻転斜頸(片方の耳の位置が、もう片方より低くなって首を傾けた状態)や顔面神経麻痺、ホルネル症候群(第3眼瞼の突出と片眼の縮瞳など)といった症状を呈することもあります。こうなると、内耳炎と混同されることもしばしばです。
近年では、オトスコープという内視鏡で鼓膜を明瞭に観察できますから、オトスコープによる鼓膜の所見だけで中耳炎と診断できることが多くなりました。
また、CTやMRIは、中耳炎の確定診断に有力であるだけでなく、中耳や周辺組織の情報も伝えてくれるので、とても優れた診断方法です。
耳科を得意とする獣医師なら、必要により鼓膜切開をして中耳から吸引した材料で、中耳炎の病態の一部を把握することができます。さらに、鼓膜切開の部位を介して中耳を洗浄するなど、治療も可能です。
しかしながら、一般に犬の耳疾患は、かなり慢性経過を経て、外耳道や中耳の組織に回復不可能なほどダメージが生じてから、2次病院である耳科を得意とする獣医師が診る、ということが多いため、既に外科手術を必要とすることも少なくありません。
その手術というのは、外耳道全部を摘出すること、そして中耳の外耳道側の骨を切除すること、さらに中耳の鼓室胞と呼ばれる骨の一部を切開し、洗浄したり、汚れたところを取り除くといったかなり大掛かりな手術です。
ただ、これまでですと100%手術が必要と言われるほど外耳道や中耳に深刻なダメージがあっても、オトスコープの活用という新しい治療法で、筆者の経験では、上記のような手術をしなくても済むケースが年々かなり増えてきました。
できるなら、元来ある外耳道や中耳を出来るだけ残したいわけですね。
先述のように、犬の中耳炎は外耳炎の感染が拡大して発症することがほとんどですが、このキャバリア種では、ヒトの中耳炎のように中耳(耳管を含む)から発症します。
症状は多様で、難聴、頸部の引っ掻き行動、耳の掻痒、頭を振る、叫び、歩様異常、頸部の疼痛、過剰または異常なあくび、耳の疼痛、顔面下垂などで、ケースバイケースのようです。
オトスコープで、鼓膜の膨隆が見られることが多く、CTやMRIで中耳に液体の貯留が認められます。
治療は、鼓膜切開と中耳洗浄が勧められます。
フレンチ・ブルドッグは、鼓膜の手前の水平耳道と呼ばれる部位が元々とても狭いだけでなく、環境や食物のアレルギーなどにより、水平耳道がほとんど閉塞してしまうことがよくあります。
このため、私共にお連れになった段階では、鼓膜切開による中耳洗浄ができないことから、中耳の外科的手術が必要となっていることが少なくありません
フレンチ・ブルドッグを飼ってらっしゃる場合、もしその子が耳を時折気にしているなら、とにかく早めの確かな対策が必要です。
(進行すると・・・)
耳ダニ感染症は、ミミヒゼンダニが耳道に感染して起こります。
このダニは、犬、猫、フェレット、そしてキツネ、タヌキなどの野生動物、場合によってはヒトも含め、直接接触によって感染します。
耳道内の表皮の剥がれたものを摂食しますが、患者には過敏に反応して、激しい痒みをもたらすことがあります。
耳道には、特有のコーヒーかすに似た耳垢がみられます。また、細菌性もしくは真菌性外耳炎、時には耳血腫の引き金になります。
診断は、耳道内の耳垢の一部を採取し鉱物油の中で顕微鏡、もしくはオトスコープという内視鏡を用いて動いているダニや虫卵を見つけることで、確定します。
治療には、様々な殺ダニ剤が用いられますが、なかでも滴下タイプの10%イミダクロプリド+1%モキシデクチンあるいはセラメクチンを、30日ごとに2回投与する方法は、対象が猫ですが効果が確認されています。
パンパンに腫れた耳
耳介と呼ばれる、本来は薄い軟骨で支えられている部分(犬種によって、立っていたり、垂れていたりします)に、血液が溜まった状態を「耳血腫」と言います。
耳血腫は、その特徴的外観と波動感から、容易に診断ができます。
耳血腫は、発症する原因がまだよくわかっていません。物理的や痒みによる刺激、また免疫学的背景も考えられています。
治療法も外科的方法、特に耳介の表側と裏側を縫いわせる「マットレス縫合」という方法、排液のためにしばらくチューブを入れたままにする方法、またインターフェロンやステロイドを注入する内科的方法が、代表的治療法になります。
いずれにせよ、早期に治療しないと、耳介の軟骨が萎縮して、くしゃくしゃな耳介になることが多いので、注意が必要です。
耳介が腫れることによって、外耳道はさらに狭くなり、外耳炎がひどくなりやすいので、外耳炎対策も併せて行います。
残念ながら、犬の耳には腫瘤という塊(かたまり)がしばしば見られます。それも、塊として認められるとは限らず、様々な形で見られます。
耳以外のところに見られる一般的な腫瘤と同じく、一見すると腫瘍であっても、腫瘍性でないタイプも少なくありません。
例えば、慢性の外耳炎で、耳垢腺という分泌腺が過剰に大きくなっていたり、痒みによる引っ掻きの刺激で結節状になっていたり、綿棒による誤ったケアで腫れていることすらあります。
また、白っぽい塊として、外耳道の奥の方に認められる「真珠種」も、まれですが認められます。
さらに、外耳道の周り(軟部組織という)が増殖していることもあります。
こうした腫瘤は、出来るだけオトスコープによって精査されるべきですし、「細胞学的検査」や必要によって「病理組織学的検査」、さらにはCTやMRIで正しく診断されるべきでしょう。
その結果、耳垢腺癌、扁平上皮癌、皮膚リンパ腫などといった悪性腫瘍であれば、その発生部位や周辺組織への影響を確認後、治療法を選択します。
ほとんどの場合、外科的に摘出手術を受けることになりますが、その手術法も様々です。ここ数年、私は「病理組織学的検査」の目的も兼ねて、「ポリペクトミー」という、内視鏡で見ながら切除する方法を、最も患者への負担が少ないことから、お勧めすることが多いように思われます。
外耳道に異物が入ると、炎症などの様々な病気を引き起こしてしまうことがあります。
症状は、犬がくびを振ったり、違和感のある側の耳を下に傾けるしぐさをを頻繁にします。
他に、外耳道が赤く腫れ上がる、鼓膜を破ってしまうなどが見られます。こうしたことで、中耳炎や内耳炎など、より深刻な病気を発症してしまうこともあります。
原因は、散歩などに行った際に草むらに入り、植物の種や虫が耳に入り込むことによって引き起こされることが知られています。しかしながら、実は体表の被毛が耳の穴に入り、鼓膜を刺激したり、刺さって起こるケースが最も多いと思われます。これまで、海外を含めこうした被毛による耳炎は知られていませんでしたので私は、「刺毛性鼓膜炎」と名付けています。
この「刺毛性鼓膜炎」は、全身麻酔をして、オトスコープという内視鏡を用いないと、見つけることすら困難と思われます。
急に首を振ったり、頭を傾けるしぐさをすれば、すぐに動物クリニックへ
対策としては、できればオトスコープと呼ばれる内視鏡で診てもらうと良いでしょう。
異物は、それが何であれ、患者であるわんちゃんに全身麻酔をかけなければ、安全に、そして確実に取り除くことができません。また、異物は既に鼓膜や中耳、さらには内耳まで炎症をもたらしているかもしれません。このため、やはりオトスコープによる正確な診断と治療が勧められます。
・全犬種が対象ですが、「刺毛性鼓膜炎」は特にパグ、フレンチブルドッグなど短頭種により多くみられる傾向があります。
各症例事にもご紹介しましたが、下記のようなしぐさをしていたら、何らか耳のトラブルを発症している可能性が高いです。手遅れになる前にすぐに専門医にご相談ください。

アメリカン・コッカー・スパニエル
もともとイギリスから輸入されたスペインの猟犬であるスパニエルにはじまり、アメリカ合衆国内で発展しました。

コッカー・スパニエル
有名な愛玩犬のアメリカン・コッカー・スパニエルの祖先犬にあたり、姿かたちもよく似ていますが、かなり頭がとがっていて口吻も長いです。

フレンチブルドッグ
がっしりとした体つきの、極めて鼻が短い小型犬です。特徴的なのはコウモリが羽を広げたような耳で、バット・イアと呼ばれます。

ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
スコットランド原産の一犬種。白一色の被毛を持つ小型のテリアで、ウェスティーという愛称で呼ばれています。

プードル
古くからヨーロッパで広くみられ、特にフランスでの人気が高く、「フレンチ・プードル」と呼称されることもあります。

トイプードル
24cm~28cmまで小型化されたプードルで、美的な要素も加味されていきながら今日の愛玩犬となりました。

外耳炎は慢性化や再発がしやすいため、ていねいな治療が必要です。また、耳道が正常化するまで。つまり、耳道や鼓膜が回復したことをオトスコープで確認できるまで通院するようにしましょう。
また、アレルギー体質による外耳炎などはより再発もしやすいので、今後のケアについてお近くの専門医に詳しく指導してもらって下さい。残念ながら、既に深刻に耳道が傷んでいる場合、CTやMRIによって、より正確に耳道だけでなく周辺組織の状態を把握する必要があるかもしれません。
従来は、大きな外科的治療が求められるケースも、オトスコープなどの活用で、手術を回避できることが少なくないようになりました。
ですが、それでも手遅れになる事もあります。そうならないように、にわんちゃんの事を考え、早期の発見と治療を心がけてください。
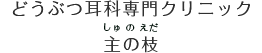
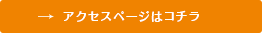
〒656-0054
兵庫県洲本市宇原2279-2
【TEL】0799-22-27700799-22-2770
【FAX】0799-22-5318
◆遠方からお越しの方へ
事前に遠慮無くお電話でご相談ください。
可能な限りご回答いたしております。
◆神戸方面からお越しの方へ
平日のETC通行料は、
神戸「柳原」〜「洲本」間で
片道2,500円(50分)です。